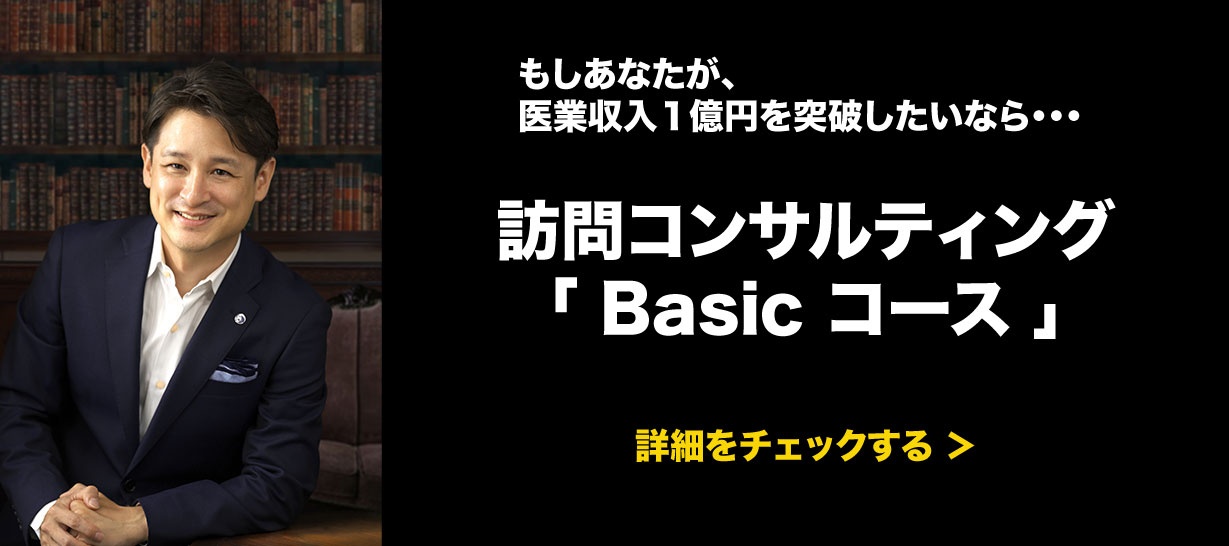川上 裕也(かわかみ ゆうや)
川上 裕也(かわかみ ゆうや)
成長する人材に共通する「ラストマンシップ」という考え方
From:川上 裕也(株式会社 歯科専門 集患アウトソーシング)
「この人は本当によく伸びるな」「必ず成果を出すだろうな」と感じるスタッフ様に出会うことがあります。
知識の吸収が早い、技術の上達が早い、患者様からの信頼を得るのが上手い──
そうした成長力のある人材に共通しているもの。それは「ラストマンシップ」という考え方です。
この言葉は、前日立製作所会長の川村隆氏の著書で取り上げられたことでも有名だそうですが、
「最後までやり切る責任感」
「自分が最終責任者だという意識」
を指しています。単に「率先して動く」とか「気が利く」といったことではなく、自分がその仕事の“責任者”であるという覚悟を持っているかどうか。
その在り方こそが、人の成長を大きく左右します。
ー「自分が終わらせる」という覚悟がある
たとえば、患者説明用の資料を作るよう指示されたとき。
「ある程度できたから、あとは誰かに渡して終わり」
「先輩がチェックしてくれて修正してもらえるからそれで良い」
ということではなく、「この資料で本当に患者さんが納得してくれるか」「現場で使えるかどうか」を考え抜いて、最後まで自分で責任を持って仕上げる人がいます。
そういう人は、仕上げの段階で起きる“詰めの甘さ”や“抜け漏れ”にも敏感ですし、改善点を自ら見つけていく中で自然とスキルが磨かれていきます。
これが「やり切る人」と「中途半端で終える人」の大きな差になります。
ー「自分は関係ない」では成長できない
歯科医院という組織では、複数のスタッフが連携して仕事を進めます。だからこそ、実は「自分の仕事はここまで。あとは他の誰かがやるだろう」という意識が芽生えやすい環境でもあります。
ですが、こうした“部分的な責任感””他責思考”では成長は止まります。
逆に、「たとえ自分の役割が一部であっても、結果が出るまでの責任は自分にある」と考えられる人は、結果が出るまでのプロセスを俯瞰的に捉え、結果が出たあとのフィードバックも忘れません。
この視点が身につくと、どんな立場でも成果を出せる人材になります。
ーラストマンシップは指導で育てられるのか?
結論から言えば、ラストマンシップは育てることができます。
ただし、マニュアルやルールだけで育つものではありません。大切なのは、現場で上司や先輩が「最後までやりきる姿勢」「責任を持つ姿勢」を見せ、言葉と態度で伝えることです。
「ここはやり切った?」
「これは本当に患者さんに伝わる?」
「完成品にするまでが自分の仕事」
そんなやり取りが日常の中にある医院は、自然とラストマンシップを持つスタッフが育っていきます。
ーラストマンシップが医院を変える
この考え方がスタッフ一人ひとりに浸透すると、医院の空気は大きく変わります。
「誰かがやるだろう」ではなく、「最後までやり切るのは自分」という意識を持つ人が増えると、仕事の質が確実に上がります。
結果として、患者さんの満足度が上がり、医院全体の信頼や収益にもつながっていきます。
そして、そうしたマインドを持ったスタッフは、リーダー候補としても非常に心強い存在になります。
技術や知識は、時間をかければ誰でも習得できますが、「最後までやり切る覚悟」は習慣と価値観の問題です。だからこそ、それを持っている人材は貴重なのです。
ーおわりに
「最後は自分が責任を持つ」
「終わるまでが自分の仕事」
このように考えられる人は、確実に成長します。
小さなことでも“やり切る”ことを繰り返している人は、どんな場面でも力を発揮できるようになっていきます。
医院を支える人材を育てるには、この意識をどう育み、評価していくかが大きなカギになります。

PROFILE
川上 裕也(かわかみ ゆうや)
株式会社 歯科専門 集患アウトソーシング
コンサルティング部門 医業収入アップ シニアコンサルタント
北九州市立大学卒業後、4つの会計事務所で約20年間、経営者の良きパートナーとして200件以上のクライアントを担当。
3件目の会計事務所で、弊社代表である渥美がGMを務める大型歯科医院の担当者となる。
当初、医業収入2億円規模だった歯科医院を、担当していた3年間で5億円以上に成長させる過程に携わった。
今までに関わった歯科医院からは、マーケティングとマネジメントを駆使して「院長個人とクリニックにお金が残るようになった!」「自信を持って経営判断を下せるようになった!」「業績が一気に回復した!」・・・などの絶大な信頼を獲得。
全国のクリニックから寄せられる経営相談に応え、東奔西走している。
趣味は、バスケットボール。